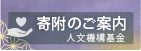現地の苦悩
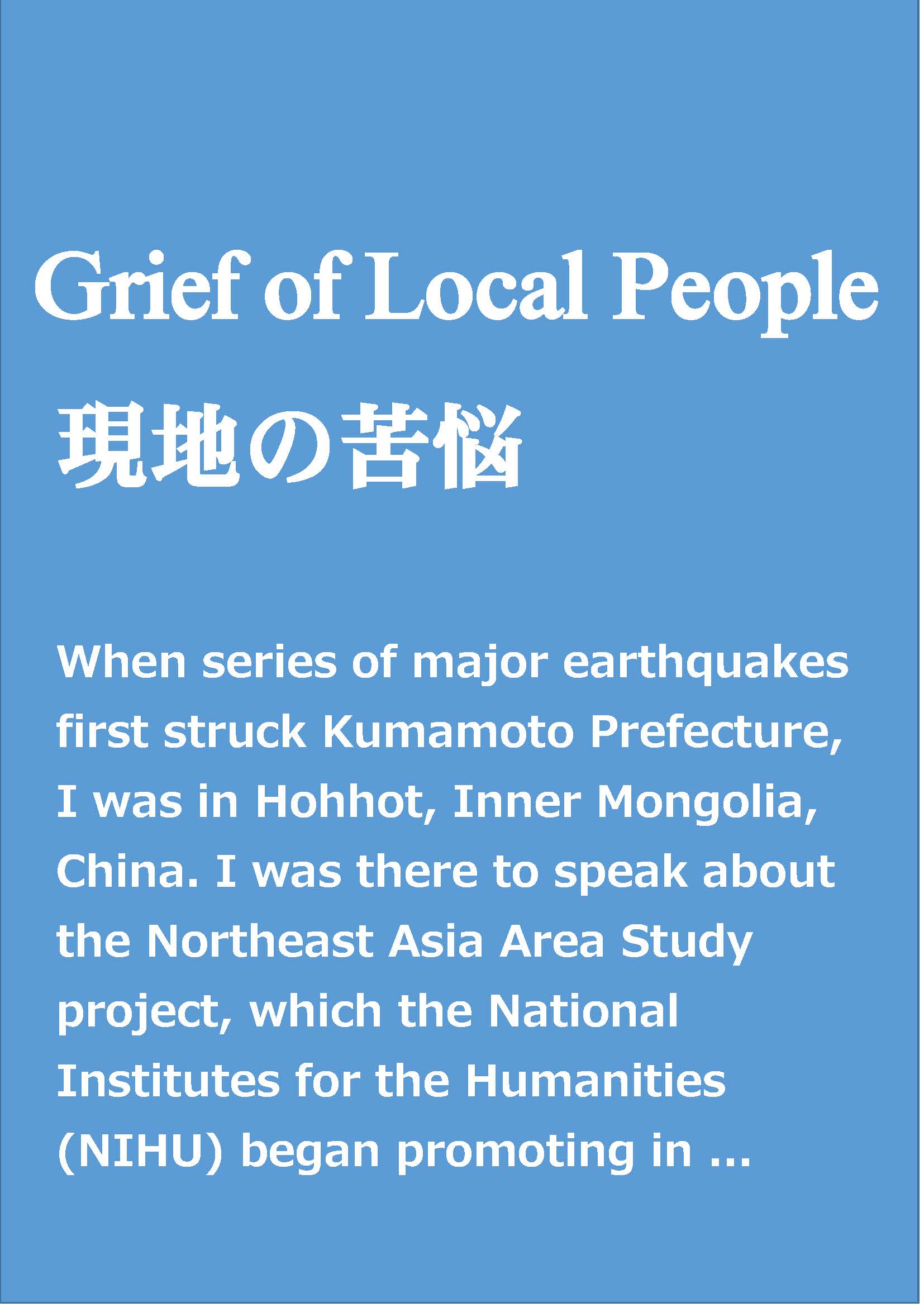
熊本で連続的な大地震がおきはじめたとき、私は中国内モンゴル自治区のフフホトにいた。人間文化研究機構(以下、NIHU)が2016年4月から推進する「北東アジア地域研究」プロジェクトを紹介し、国際共同研究への参画を促すためである。現地の研究者にはぜひ積極的に参画してもらうべきだろう。
ちょうど内蒙古大学から講義を依頼されていたので、講義枠のひとつを用いてNIHUの同プロジェクトを紹介した。この研究プロジェクトは、5つの機関がそれぞれ異なる課題を担当し、相互に連携する体制をとる。まず、NIHUを構成するひとつの機関である国立民族学博物館が中心拠点となる。その具体的な研究テーマは「人とモノとシステムの移動・交流からみた自然と文明」である。NIHUのもうひとつの博物館である国立歴史民俗博物館と協業する。北海道大学のスラブ・ユーラシア研究センターは国際政治を担当し、「域内連携体制構築をめざす国際関係論」の研究を推進する。東北大学の東北アジア研究センターはNIHUの総合地球環境学研究所と協業して「環境問題・地域資源に関する文化と政策」の研究に取り組む。富山大学の極東アジア研究センターは持続的な経済開発をめざして「国際分業の進化と天然資源の持続可能な利用に関する研究」を担当する。島根県立大学の北東アジア地域研究センターは歴史的アイデンティティに焦点をあてて、NIHUの国際日本文化研究センターと協業して「近代的空間の形成とその影響」を研究する。このように、国際関係、経済協力、環境問題、文化複合、歴史認識などの課題を分担する5つの機関が連携して総合的な地域研究を推進する、というプログラムである。
現地の研究者たちは、個人的な関心に応じて適切な各機関チームの国際メンバーとして研究成果を発信することもできるだろう。また、組織的に研究課題を設定し、国際的なネットワークのひとつの拠点として協業することもできるだろう。
例えば、「フフトグの総合的研究」があげられる。フフトグとはモンゴル語で青旗を意味し、「満洲国」(中国では「偽満洲国」と表現される)で刊行されていた、モンゴル語の新聞である。その編集にあたっては、日本人も大いに関与していたことが知られている。日本ではそのデジタル化を進め、公文書などを通じて設立経緯などを詳細にする一方で、現地研究者たちは、農牧業から文芸まで幅広い記事を分担して読み込むことができる。一つの資料群に焦点をあてることによって、広い分野にまたがり、日本と現地との協業が可能になる。討論を通じて、そんな具体的な事例も浮かび上がってきた。
吉林大学でも中国東北地方の諸大学から近代社会史の研究者たちが集う学術交流会が開催された。そこで、私は、自分自身のこれまでの研究業績のうち、近代社会史に関係するテーマの論文を紹介するとともに、ここでもやはり同プログラムを紹介した。吉林大学のある長春市はかつて新京と名付けられ、偽満洲国の首都であった。そのため、ここでの近代社会史研究はとりわけ日本との協業が欠かせない。そんな現地研究者の希望がひしひしと伝わってきた。GNPが日本を抜いて世界2位となった中国に対して、資金の提供はさして必要ではない。情報の共有こそ必要なのである。
ところで、フフホトで同プラグラムを紹介したあと、一人の学生が質問した。自分の故郷で生じている開発に伴う環境問題についてどのように取り組めばいいか、と。草原での環境破壊といえば、2011年におきた、デモが思い出される。鉱山開発の周辺では自然環境が極端に劣化しているため、放牧できなくなった牧民たちが反対運動を起こし、これを制圧しようとしたトラックが牧民の1人を轢き殺した。このニュースに呼応して、フフホトや北京でもデモが行われた。以来、政府の監視が厳しくなっているから、環境問題の研究は慎重に進めなければならない。中国の外にいる私がどうしてうかつに学生たちを煽ることができようか。
先のデモそのものは収束したが、同様の事件は頻繁に各地で生じている。まさに私が訪問しているあいだ、人びとの携帯電話に次々と飛び込んできていたのは、ジャルート旗での小競り合いの様子であった。ジャルート旗は、通遼市の西北にあり、ホーリンゴルの炭鉱開発のために移住を強いられた地域である。私が2013年に訪問したときも周辺の煙害がひどかった。しかし、汚染問題は大気にとどまらず、もっと深刻である。毛のない裸の子ヒツジや一つ目の子ヤギなどが産まれている。真実を求めて立ち上がった牧民たちを警官が阻止するシーンは中国のウェイシン(微信)を通じて拡散したが、やがて現地からの情報発信は途絶えた。噂によれば、道路閉鎖に加えて情報網も遮断されたようだ。
地震でもないのに、交通路や情報網が絶たれるのは、社会災害である。社会災害による現地の苦悩に対して、私たちに何ができるというのか。どんな研究にはもちろん限界はつきものであるからこそ、せめて現地の人びとの苦悩を知っている研究者でありたい。
人間文化研究機構 理事 小長谷 有紀