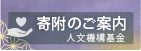インタビュー・シリーズ①『ロバート キャンベル国文学研究資料館新館長』

インタビュー・シリーズ①
ロバート キャンベル国文学研究資料館新館長
インタビュアー
人間文化研究機構長 立本 成文
国文学研究資料館(以下、国文研)では、2009年度から2016年度まで8年間館長を務められた今西祐一郎氏が退任され、2017年4月よりロバート キャンベル氏が新館長に就任されました。2014年度から10年計画で始まった大規模学術フロンティア促進事業「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」もいよいよ軌道にのり、その成果が待たれています。これからの国文研は、厳しい財政状態のなかで国内外からの期待にどう応えていくか、人文機構長が新館長に抱負を伺いました。
1.国文研のこれからのミッションと評価指標
(立本) 「月刊えくてびあん」の中で、サレジオ大学図書館(※1)の「マリオ・マレガ文庫」発見の記事を拝見し、キャンベル先生が国文研と非常に深い関係にあるということをあらためて知りました。先生に館長になっていただいて非常に喜んでいる次第です。
新しい館長として第一に国文研の大きな柱としてのミッションと評価指標について、第二に機構や機関のグローバル化について、第三に大学共同利用機関としてのあり方について、お聞きできればと思っています。
(キャンベル) ありがとうございます。国文研との関係は、九州大学におりましたころ、国文研の文献調査事業(日:http://www.nijl.ac.jp/pages/investigation.html)(英:https://www.nijl.ac.jp/en/)に加わったことがあります。また、1995年から5年間ほど助教授として勤めたことがありますので、古巣に戻ってきたという格好です。
国文研のように日本文学をデータとして捉える前に、マテリアルとして研究の材料にしていくということ、つまり、実物の文献資料を当時の社会の中で使われていたものとして研究対象として収集、調査していく機関は、世界的に見て国文研以外ないのです。

(立本) そうですか。そうするとやはり国文研が最初の資料館として、戦後ばらばらになったものを集める、というミッションが良かったのですね。
(キャンベル) それは戦時中に研究生活を送っていた先達が、多分ある危機的意識を持って1960年代から準備してくださったと思うのです。ですから、他の北東アジアの国々に比べて紙媒体の資料が残りやすかったさまざまな歴史的経緯や文化的な構造が日本にあって、人災、天災をくぐり抜けてきた資料を戦後まず集めました。そして、今後何があっても人類の財産として継承していくという保管機関と研究機関が合わさった形として国文研が始まったことは、50年になろうとしている今になって振り返ると、大変幸いなことです。
今からそれをつくろうと思っても、恐らく理解を得難いと思うのです。短期的、中期的なプロジェクトベースではまずできない。国家百年の計の一つのスペックの中でまず始まり、そしてそれが継続されたことが重要なのです。

(立本) では、研究所の次の50年をどういうふうにお考えでしょうか。
(キャンベル) 鬱蒼とした森のような文化資源と人脈があります。これらを原材料として、これから研究や新たな文化の創成にどのように活用していくかということが、私たちが今、社会から付託を受けている一番大きなことだと感じます。ですから、今あるものをどのように整理して、言語文化の最も重要な証言として実際に運用していくのか。そして日本文学研究者だけではなく、他の人文研究者や若い学生たち、そして他分野の方々にも門戸を広げ、言語を越えて交信していくことが必要です。
(立本) 相互発信という意味で「交信」ですね。さて、今の評価指標ですと、研究者が「アチーブメント、達成した」と言ってその達成した指標を見せないと世間が納得しないということになっています。その点は、国文研のようにじわっと国民の基礎力を作っていく分野では非常に難しいと思うのですが、それはどうお考えでしょう。
(キャンベル) 私は、見せにくいという意識はないです。国文研の事業は、世界中にある日本の明治以前の文献を見いだし、写真で撮り、実物も収集し、それを私たちの共有のマテリアルとして研究する。一方ではそれを携えて、他分野の研究者やクリエーターとします。彼らからインスピレーションを得ながら、共に地域社会を活性化させ、新たなる文化の創成に関わっていくことです。たとえば、古典籍にはかつて災害によって社会が部分的に壊れたとき、あるいは危機にさらされたときに、どのように立ち上がったのかという蘇生の知恵がたくさんあるわけです。ですから、絶えず静かな海底のように、国文研が半世紀近くかけて多くの人々の協力を得ながらこつこつと豊かな養分を堆積させていく事業はこれからもやります。それ自体は見せにくく、ポイントとしては立たせにくいかもしれませんが、そこから必ずわれわれは、眼に見える成果を出していきます。
2017年3月の新聞にありましたが、国立極地研究所と国文研の共同研究で、オーロラの研究をやっていますね。13世紀の藤原定家の『明月記』は古典中の古典です。そこには「赤気(せっき)」という言葉があり、小倉山荘(※2)辺りで「山が燃えるように赤気が見えてきて、恐ろしい、まがまがしい風景だ」と書かれています。あれは彗星とされてきましたが、私たちの文献研究と極地研の知見、調査を合わせると、実はそれはオーロラで、太陽風と地磁気の関係で13世紀には日本の上空で見えていたということが分かりました。
そうすると、鎌倉時代の例えば和歌表現に現れる、さまざまな色彩や光、あるいは宗教、祈り、救いというものの感性、感覚が、オーロラ観察体験を社会で共有していたことでどう変化していたのか、私たちの理解が少し変わるかもしれません。
そういったたくさんの材料を持続的に発掘、整理、公開するために、国文研としては上手に種子をまき、あまり過剰に除草することなく、タンポポの間から面白い花が咲くよう整備していきます。私はそれが最も見えやすいと思います。
(立本) 評価というと指標にばかり目が行きますが、われわれとしては人文学の知を社会に広める、人文知コミュニケーターを育成し、発信から得たフィードバックを評価につなげる取り組みを開始しました。先生がご発案の古典インタプリタも評価に結び付いていくのではないかと思いますが、いかがでしょう。
(キャンベル) 以前は、社会に求められるさまざまな思考やスキルを獲得する教育教科として日本文学があったのですが、1990年代から日本の大学では文学部が次々と改組され、本格的に学べる場が減っていきました。それにより、若い研究者たちが、例えば『源氏物語』や夏目漱石だけを教えることで、一生を全うすることが難しくなっています。しかし、彼らは重要な日本の底力、教養を支えている立場の人たちです。大学の中で、あるいは博物館、美術館、自治体やメディアの中でも働き、評価されるためのスキルを広げていく必要があると私は思うのです。
外国文学だと、外国語に堪能な人が小説や哲学書などを翻訳することが評価の対象になるわけです。しかし、日本文学を崩し字から判読し、本文を校訂して、注釈を付け、現代語にすることは、翻訳以上のスキルを必要としますが、日本で評価されません。
若い研究者たちが、膨大な日本の古典知の中にどういったものがあるか探求し、現代人がアクセスできるテキストにして、他分野の人に供用しながら新たな発想や創成につなげていくという力を、スキルとして確立させたいです。
(立本) では、人文知コミュニケーターも古典インタプリタも同じ発想ですね。機構としては、機構の6機関がどんどん翻訳しながら発信することが評価につながる、それしか評価をしてくれないと考えています。

(キャンベル) 古典インタプリタという概念を日本の各学会に浸透させ、それぞれの大学や教育機関が資格として認定できるようなプログラムを作らないといけないと思います。それができるだけでも一つの評価の対象にもなると思います。古典インタプリタがいて、無尽蔵にある日本の古典知、人文知から新たな発見や救い、あるいは挑戦が生み出され、そこに実際に着手されるところまで私たちが見届ける義務があると思うのです。
2.機構と機関のグローバル化
(立本) 古典インタプリタや異文化理解は、まさにグローバル化の話になります。今、外部からグローバル化という評価指標軸が設定されていますが、日本文学や日本文化のグローバル化とは何なのでしょう。外に対して何をグローバル化していくのか、その方向性はどういうふうにお考えでしょうか。
(キャンベル) まず、グローバル化できるような環境を整えることが大切です。何をやるかということを私たちは一つ一つ決めて示すべきではないと思います。これは翻訳することもそうです。日本では数年前、日本文学を翻訳して、短期間にたくさんの作品を出版して普及させようということを政府主導でやろうというプロジェクトがありました。そのときに、例えば小説であれば何を翻訳するのかを委員会で決めていたのです。これは、私は駄目だと思います。世界の各地域、文化圏の中で求めるものが違います。
ですから、発信するという言い方に私が違和感を持つのは、発信するということはこちらの概念枠の中からしかできないわけで、どのような要請があるのか、どこで社会と連結できるのか、そこから考えないといけないと思います。まずは共用できる資源をどのような形で選択的に多言語化させるのか。作品を完全に翻訳するのではなく、たくさんの作品の解題やあらすじを、たとえば日本語で800字書いて、それを他言語に翻訳する。こちらが決めて発信するのではなく、双方向でどのようなものがそれぞれの文化や時代の中で求められるか、まず棚卸しをしながら決定していくことをやっていきたいと思います。
3.大学共同利用機関の在り方について
(立本) それが一番着実な方法だと私も思います。さて、国文研は50年前にできて13年前に大学共同利用機関になったわけです。大学共同利用機関は、文科省の説明では世界にユニークな組織であるという。これは本当でしょうか。

(キャンベル) そのとおりですね。全ての大学の教職員や学生に開かれ、かつ一方的に何かを提供するのではなく、各大学が目指す研究の在り方に沿って、学科や研究組織などと連動、連携しながら大学を強化していくことがミッションとしてあると思うのです。
一つ、自分も当事者として大きな成果だと思うのが国文研が作った調査員の制度です。地域にいる同じ分野の研究者たちが大学を越えて合同で、その地域にどういう資料があるか調査し、一緒に研究していくというもので、まさに一大学ではできないことです。そしてこの調査に参加した研究者、教育者たちは、そこで得た知見や経験、人脈を職場で活かせるのです。北部九州で10年近く調査員を務めていましたけれども、そのおかげで随分、九州大学の教員としての私の価値、能力は上がったという意識があるのです。このような事業は他の国にないですね。事業の意味をもっと積極的に考えることで、新たな学問領域の創成につなげられると思うのです。
(立本) そういう新しい領域を開拓していくのが、大学共同利用機関の存在理由ではないかと思うのですが、国文研はそういう意味では非常に地道に、協力関係を作ってきたことがよくわかりました。この取り組みは研究者コミュニティには知られているのですよね。
(キャンベル) はい。海外のコミュニティにも知られています。それは素晴らしいチャンスです。私たちは、地道に先達が作り上げてきたものの中に、今浸っているわけですから、多くの国民、納税者、子どもたち、その保護者にも知ってもらいたいと思うのです。
研究者コミュニティと一般人に二分化する発想が日本の学会にはありますが、この二項対立はネガティブなもので生産性がないと思うのです。今日ここで、私は専門家ですけれども、角度を30度変えれば一般人なのです。歴史研究に対しても、地理研究に対しても、ましてや極地研究に対しては究極の門外漢です。ですから、私が専門家として向かっている10度の角度の中だけでは、新しい領域は生まれない。
ですので、グラデーションのある一般の人たちの多様なニーズに目を向けることで、出版物を手に取ってもらい、あるいはウェブサイトのハッと驚くような図像やテキストから何かを得てもらうことができます。研究集会を知らせることも必要だと思います。そういうことをどんどんやっていかなければならないと思います。
(立本) キャンベル先生、本日はどうもありがとうございました。
※1 正式名称は、教皇庁立サレジオ大学 ドン・ボスコ図書館(http://biblioteca.unisal.it/)(Biblioteca Don Bosco, Università Pontificia Salesiana)ローマ郊外にあり、マレガ神父が収集した日本の古文書などを収蔵している。
※2 鎌倉時代初期の公家であり、歌人でもあった藤原定家の山荘。京都市右京区嵯峨の小倉山の山麓にあったとされる