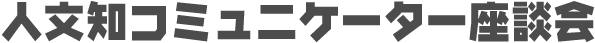今後のテーマ:感染症による死とどう向き合うか


金 私が具体的に取り上げたいテーマの一つに医療人類学的な視点があります。今は、人間がまるで生物学的というか、医療的な存在として語られる風潮が強くなっていると思うんですね。いかに感染を防いで、いかに生物学的な命を維持するかが大事。もちろん、それはそうなんだけれども、同時に社会文化的な存在でもある人間が、この時代をいかに生き抜くかという視点が抜け落ちている気がします。ようやく「withコロナ」という言葉が出てきたましたが、どちらかというと経済活動が中心になっていて、現代の人間は生物学的か、経済的な存在でしかないのかと思うと、本当にモヤモヤしてしまいます。
私の研究テーマである死と葬儀という側面からみても、同じ現象が起きていて。少し説明させていただきますと、今の社会では臨終までの過程は医療化されていると言えるけど、一旦遺体が遺族や葬儀業者に渡ると、社会文化的な死の処理のプロセスへと移行します。しかしコロナによる遺体は、感染の危険性が残っているという理由で、医療的な存在としてあり続けないといけなくなっている。ということは、これまでの社会文化的な死との向き合い方は許されないわけです。
堀田 遺体と対面できない、灰になった状態で帰ってくる、亡くなった方が使っていた物も燃やさなければならないという、常時では起こり得なかった死との付き合い方が現れていますよね。コロナは生活のあらゆる側面と関連していて、それが文化的なこと、例えば最期のお別れに顔を見ることができないという事態に及んで、逆にこれまで日本人がいかにそれに重きを置いてきたかが立ち現れている。
河合 日本古代・中世は、死は穢(けがれ)を招くとされ、家族であっても死に目にあえないことがありました。特に貴族層は、誰か死にそうになったらその場を離れて、別のところに行かないといけないこともありました。それにも関わらず、亡くなる妻を抱きかかえたままにしていた天皇もおり、それによって政治的なものが全部ストップする恐れがあったという話も残っています。やはり、いつの時代でも、大切な人の死に目にあえないということは辛いことだと思うんです。今回のコロナ問題を抱える私たちも、会いたいけど会えないという状況にいつ直面するか分からないわけですよね。そういう、死ぬ人を支えて最期まで見届けたいけどできないという葛藤は、前近代にもあったということをふと思いました。
金 古代や中世においていかに死に対処してきたのか、また文学作品には伝染病による死がいかに描かれているかなどにもとても興味があるので、人文知コミュニケーター同士の学際的な企画として展開していけたら面白そうですね。河合さんの話はケガレとハレというところにつながると思うんですが、これは医療とは一見異なるものに聞こえても、どちらも一つの世界観だというふうに捉えれば、同じレベルで解釈することもできます。